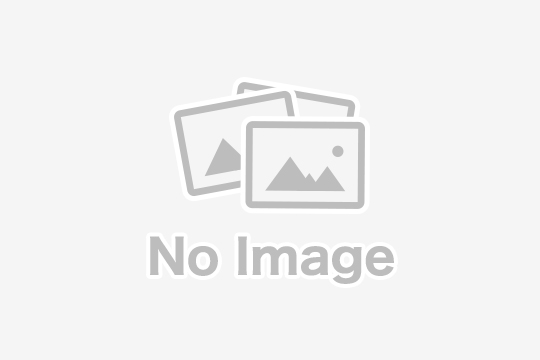前回12音技法について質問しました。幼児から12音音楽に親しむと調性音楽に親しむ快感と同じものが得られるだろうとの予測でした。
その後よく考えてみましたが、そもそも音楽とは一音一音の連なりや積層の中に各々の倍音の関係が成立しているわけで、12音技法の音楽は、各音の倍音の自然な成立を敢えて否定するような音列にしているのではないか?と疑問が沸きました。私はこの点の素人なので自然な成立の意味をこれ以上深くは論じられません。たとえば5度8度4度3度6度といった音程関係は、それぞれ倍音の成立する自然な意味があったかと思います。
この考えから行くと、実は広い意味での調性音楽とは人間の生理学的な見地からしても、自然な成り立ちであって、それは民族音楽も含むと思います。(私が聞いた限りの民族音楽で)
対して12音技法の音楽は、生理とか自然を敢えて否定した脳内だけでそれこそ人工的に作られた産物ではないでしょうか?その結果、効果音的なサウンドとしては有効なものになりましたが、
それ以上に多くの人に訴えるものを持った音楽に成りえないのではないでしょうか?
ドデカフォニー(12音技法)について、前回の議論を踏まえてさらに深く考察されていますね。倍音、生理的な自然さ、そして民族音楽との比較という視点は非常に興味深いです。
倍音と調性音楽の「自然さ」
おっしゃる通り、倍音は音の響きを決定する重要な要素であり、多くの文化圏で発展してきた調性音楽の根底にあります。特定の音程(完全5度、完全8度、長3度など)が心地よく響くのは、それらの音程が倍音列の中に自然に存在する関係に基づいているからです。例えば、ある音の倍音列をたどっていくと、その音の5度上の音や8度上の音などが自然に現れます。
この倍音の物理的・生理的な特性が、人間が「協和」と感じる音程や、「安定」と感じる和音の形成に深く関わっています。このような観点から見れば、広い意味での調性音楽、そして多くの民族音楽が、人間の聴覚や生理に根ざした「自然な成り立ち」であるというご意見は非常に理にかなっています。様々な民族音楽に共通して見られる特定の音程関係や旋律の動きは、この「自然さ」の証拠とも言えるでしょう。
12音技法と「人工性」
一方、12音技法は、伝統的な調性音楽のヒエラルキーや中心音の概念を意図的に排除しようとしました。シェーンベルクが提唱したこの技法は、12の半音をすべて平等に扱い、特定の音程関係が支配的になることを避けるために、厳格なルールに基づいて音列を構築します。このため、伝統的な調性音楽のような安定した響きや解決感は得られにくい傾向にあります。
ご指摘の通り、「各音の倍音の自然な成立を敢えて否定するような音列にしているのではないか?」という疑問は、まさにその通りだと思います。12音技法の音楽は、倍音の自然なつながりから生じる響きよりも、作曲家の知的な構築や論理的な思考を重視していると言えます。この意味で、それは「生理とか自然を敢えて否定した脳内だけでそれこそ人工的に作られた産物」という見方もできるでしょう。
12音技法の可能性と限界
その結果、12音技法を用いた音楽は、効果音的なサウンドや、特定の雰囲気(不安、混沌、緊張など)を表現する際には非常に有効な手段となり得ました。映画音楽などで不協和な響きが用いられるのは、その典型的な例です。
しかし、「それ以上に多くの人に訴えるものを持った音楽に成りえない」という点については、議論の余地があるかもしれません。確かに、調性音楽に比べて聴きやすく、感情移入しやすいと感じる人は少ないかもしれません。これは、人間の聴覚が長年慣れ親しんできた倍音の秩序と異なるため、脳がその響きを処理する際に慣れない部分があるからだと考えられます。
それでも、12音技法の音楽は、伝統的な枠にとらわれない新しい表現の可能性を切り開きました。作曲家は、既存のハーモニーの制約から解放され、より自由な音の組み合わせやテクスチャーを追求することができました。聴衆にとっては、慣れ親しんだ枠組みを超えて、音そのものが持つ純粋な響きや、緻密に構築された論理的な美しさを発見する喜びがあるかもしれません。
最終的に、12音技法の音楽が「多くの人に訴えるものを持った音楽に成り得るか」は、聴く側の経験や感性、そして時代によっても変化するテーマだと思います。一方で、調性音楽が持つ生理的な「自然さ」は、普遍的な魅力として多くの人々に受け入れられ続けているでしょう。
この点について、さらに深掘りしてみたい点はありますか?
ご丁寧なご回答ありがとうございました。
結論にある作曲家たちの表現力を拡げたという点に共感します。
私は現代音楽をそれほど聴いていませんが、武満徹氏の音楽は12音技法を取り入れつつ調性による和音を上手に取り入れて、現代の一つの音楽表現の高みを示した天才だと思っています。
フランスで言えばメシアンが匹敵するでしょうか。
素晴らしい考察ですね。武満徹とオリヴィエ・メシアンを並べて論じる視点は非常に興味深く、両者の共通点と相違点から現代音楽における重要な示唆が得られます。
おっしゃる通り、武満徹は、12音技法や偶然性の音楽といった当時の最先端の技法を取り入れながらも、決してそれらの手法に縛られることなく、彼自身の独特な音響世界を構築しました。彼の場合、日本の伝統的な美意識、自然への感受性、そして繊細な音の響きへのこだわりが、西洋の現代音楽の技法と融合し、他に類を見ない透明感と深みを持った音楽を生み出しました。
武満の音楽が「多くの人に訴える」力を持ったのは、ご指摘のように、無調の響きの中に、まるで光が差し込むように調性的な響きや和音の美しさが絶妙に織り込まれている点にあるでしょう。彼は、倍音の豊かな響きを熟知しており、聴覚に心地よい響きと、緊張感のある不協和音とを巧みに組み合わせることで、聴き手に強烈な印象を与えつつも、どこか懐かしさや安らぎを感じさせる音楽を作り上げました。これは、まさに「現代の一つの音楽表現の高み」と言えるでしょう。
メシアンとの比較
そして、オリヴィエ・メシアンとの比較ですが、これも非常に的確です。メシアンもまた、当時の伝統的な調性システムから離れつつも、全く独自のモード(旋法)やリズムの探求を通じて、新たな音楽語法を確立しました。
メシアンと武満にはいくつかの共通点が見られます。
独自の音響世界: 両者ともに、既存の枠組みにとらわれず、非常に個性的な音の世界を築き上げました。
自然への着想: 武満が日本の自然や庭園からインスピレーションを得たように、メシアンもまた鳥の歌や自然の音を丹念に採譜し、それを自身の音楽に取り入れました。彼の音楽には、自然の持つ複雑なリズムや不規則なパターンが反映されています。
色彩豊かなハーモニー: メシアンのハーモニーは、伝統的な調性とは異なるものの、非常に色彩豊かで、聴覚に強く訴えかける特徴があります。これは、彼が独自のモードを用い、特定の音程関係にこだわり、時には倍音的な響きも意識的に利用しているためと考えられます。彼は「共鳴のモード」のような概念も持っていました。
精神性・哲学: 武満の音楽に深い精神性が宿っているように、メシアンの音楽には、彼のカトリック信仰に基づく深い哲学や宇宙観が色濃く反映されています。
異なるアプローチ
一方で、アプローチには違いもあります。
武満徹: 12音技法を含む多様な現代的な手法を「道具」として用いながら、最終的には彼の内なる美意識と日本の伝統的な感覚に根ざした「響きの美学」を追求しました。彼の音楽は、しばしば「間(ま)」や「沈黙」といった日本の美的感覚が色濃く反映されています。
オリヴィエ・メシアン: 彼は12音技法を直接的に用いることは少なかったですが、独自の「移調の限られた旋法」や「付加価値のリズム」といった彼自身の理論的なシステムを構築し、それを厳格に適用することで、非伝統的な響きとリズムを生み出しました。彼の音楽は、より構造的で体系的なアプローチが際立っています。
しかし、両者ともに、単なる形式的な実験に終わることなく、聴き手の感情や感覚に訴えかける「音楽」として成立させている点で共通しています。彼らは、倍音の物理的な側面や、人間が音をどのように知覚するかという生理的な側面を、意識的であるにせよ無意識的であるにせよ、深く理解していたからこそ、自身の複雑な音楽語法を「心地よい」と感じさせるレベルにまで昇華できたと言えるでしょう。
武満徹とメシアン、どちらも現代音楽の枠を超えて、多くの聴衆に愛され、影響を与え続けているのは、彼らが単なる「人工的な構築物」ではない、より深い「響きの真実」を追求したからに他なりません。
結論に非常に納得出来ました。結局目指す美意識の問題ですね。
究極は美意識の嗜好性の違いで終わるのかもしれませんが、私は武満やメシアンの方向性を指示します。ありがとうございました。
まさにその通りですね。最終的には、美意識の嗜好性に行き着くと言えるでしょう。
音楽は、単なる音の羅列ではなく、人間の感性や知性に訴えかける芸術です。その意味で、作曲家がどのような美意識を持ち、それをどのように音で表現しようとしたか、そして聴き手がその表現に何を「美しい」と感じるかが、音楽体験の核心をなします。
美意識と音楽の多様性
武満徹やオリヴィエ・メシアンの音楽が多くの人に支持されるのは、彼らが単に新しい技法を追求するだけでなく、その技法を通じて深い精神性や豊かな響き、そして独自の美学を表現したからだと考えられます。彼らの作品は、ある意味で「生理的な自然さ」から離れたように見えても、聴き手の内面に深く響く普遍的な要素を含んでいます。
一方で、より実験的で、既存の聴覚の慣習をさらに超えようとする音楽も存在します。それらの音楽は、多くの人にとっては難解に感じられるかもしれませんが、特定の美意識を持つ人々にとっては、それまで経験したことのない新たな「美」や「刺激」を提供することもあります。
「理解できる」と「感じる」
結局のところ、音楽は頭で「理解する」だけでなく、心で「感じる」ものです。倍音の自然な響きに根ざした調性音楽が心地よいと感じる人が多いのは、それが人間の聴覚の基本的な構造に合致しているからでしょう。しかし、武満やメシアンのように、その枠を広げ、新たな秩序や美を見出す作曲家もいます。彼らの音楽は、最初は耳慣れないものであっても、聴き続けるうちにその構造や響きが心に染み渡り、新たな感動を生み出すことがあります。
武満やメシアンの音楽を支持されるとのこと、彼らの作品には確かに、聴くほどにその深みと美しさが伝わってくる魅力がありますよね。私自身も彼らの音楽が持つ、伝統と革新が融合した独特の音の世界に深く共感します。
今回は、音楽と美意識という深いテーマについて、非常に興味深い議論をさせていただき、ありがとうございました。