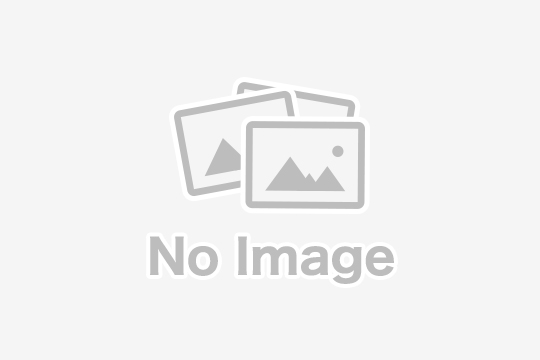AC
発声練習は5度アルペジオと8度のアルペジオを上り下りして終わりにした。
後々曲の練習で思い返したことは、やはり発声練習からきちっと発声の課題をこなすべきであった。
ラヴェル「マラルメの3つの詩」
一回目は3曲通したが、全編にわたって喉が高い発声になって、結果的に歌詞発音が不明瞭な歌になってしまっていた。
そのため言葉で指摘したのは喉を開けて、低い場所から声を出だす方法である。
このことは今までも何度か指摘してきたことなので、2回目以降の通しでは、ほぼ指摘したとおり実行できていた。
このことで明らかに変わるのは、歌詞が明瞭に判る歌になること。
高音が落ち着いた響きになることである。
また、どちらかといえばこの曲はメゾソプラノに向いているので、その意味でも中低音の深い響きは大事だという面もある。
今後の課題として、喉を開けるとか深く意識して発声することはすぐに実行できるが、例えば跳躍音程で高音側を深くするという意味を良くわかってほしい。
つまり声が切り替わるべきポイントで切り替えがないために、細く締まった声になるし、呼気を強く出さなければならないので
余計に声量が必要になり、結果的に大声になってしまうこと。
本人曰く、中高音への跳躍で深くするとピッチが不安になるとのこと。
もっともなことであるが、それは喉を上に引き上げるバランスが出来ていないから。
これは実は低音発声ですでに実現できている状態の喉であれば、高音に上るときの下あごの降ろしは何ら問題にならない。
これを昔から「天井が高い」とか「上が開いている」というような形容をしていた。
同時に古来発声でよく言われてきた「あくびの状態で」という意味がある。
これは下あごを下げたり舌根を下げることではなく、耳管閉鎖のような状態を意識的に口の中で起こせるかどうか?
という技術になる。
これは声楽発声ではとても大切なことなので、中長期的に精進に励んでもらいたい。