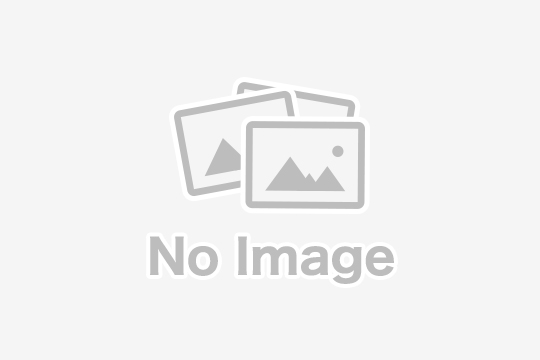SNT
発声練習
下降形5度スケールで5点Gまで上がり4点Cを下限として発声練習を始めた。
次に5度上行形スケールで、5点bまで上がり下がりの練習となった。
特に課題を設けた練習は行わなかった。
ラヴェル「ヴォカリーズ・エチュード」
まず冒頭のテーマのリズムを正確なリズム感で歌うこと。
ピアノを頼らないで、アカペラで正確に歌う練習をした。
手で2拍子の拍節を叩いて、きちっと歌えるように。
それから頻繁に出てくるフレーズ中の32部音符はこぶしのようなものなので、思っているよりも鋭く素早く歌うこと。
必然的に技術力のレベル内として、弱声を狙わない方が良いだろう。
基本的にこのメロディはクラシックのアリアと違って、民謡を表現していることをイメージした方が良い演奏になるだろう。
後半の長いメリスマは、基本的に一息で歌ってほしい。
そのために、ラヴェルはRubatoと記載しているわけである。
つまり速く歌うこと、最後にRitをかけて辻褄を合わせると良いだろう。
ラヴェル 民謡集より「フランスの歌」
速すぎないテンポ指示だが、音符の読みに遅れが出る歌い方なので、基本的にテンポアップを指示した。
具体的には3拍子を3拍に感じないで、1拍に感じて歌うこと。
つまり1小節1拍という感じ方である。
今回は指摘しなかったが、ほぼ換声点直前の音域なので、換声を意識できると良い。
意外と頭に響かせない歌い方の方が、音程感も良いものである。
ラヴェル「3羽の極楽鳥」
ピアノ伴奏がとてもシンプルで和音も薄いせいもあるが、声のピッチが表現に密接することを強く要求される音楽である。
つまりこの音楽の曲調は、なんとも言えず物悲しい雰囲気と寂しさに溢れていると思う。
そのようなメロディをどう歌うか?
発声の根本技術という側面が大きいのだが、現実的な対処としてピッチを高くしないで低めに構えること。
という提案をした。
こが思いのほか功を奏して、音楽の持っている表現が自然に出る歌声になった。
後は、有節かきょくであるから、切れ目のところのピアノ伴奏の弾き方には工夫がいる。
つまり、歌のフレーズが終わってそのままインテンポで行ってしまうと、座りの悪い滑った感じの音楽になってしまうのである。
平たく言えば歌い手が次の節を歌いだすための、ブレスのタイミングを誘うようにRitをうまくかけてやるのである。