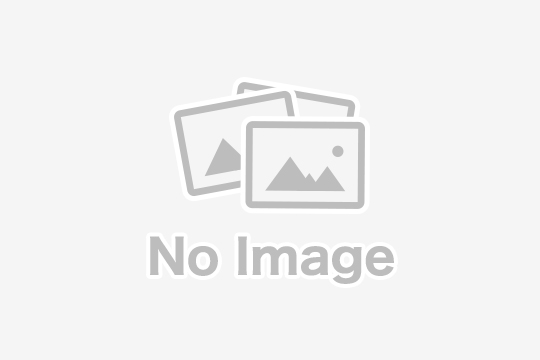AC
発声練習
下降形の5度、上行スケールの5度を5点Gまでを境に練習した。
声質は安定していたし、換声点の処理も悪くない。
ただ実際の歌になるときに、この点を指摘し、修正することになった。
マラルメの3つの詩
1「ため息」2「空しい願い」3「脆いガラス瓶の尻から飛び出て」
今回もカラオケを使ったり部分的に私が弾いて、リズムを正しく歌うことや音程感の調整を練習した。
最終的にそれぞれ通したが、大分仕上がった感じであった。
最終的には、前回指摘したように、譜面ではなく歌詞カードを見て歌えるようになると良い。
それは、この作品を日本語で歌う時に、演劇性が必須となるからである。
歌曲集全体の声の扱いや表現方法の主体となる技術について
全体に言えるのは中音域までのA母音がややこもり気味な点。
良い声質だが、歌詞が不明瞭になるデメリットがある。
また、歌詞を明瞭に伝えることが本義として歌うことを考えた発声に意識を持ってもらいたい。
そのための母音の明るさや、子音の出し方である。
それは単にそうしないと、歌詞を演劇的に読むことと歌うことのミックスを実現してほしいからである。
そうでないと、このような曲を歌って日本語歌詞が判ってもらわないと、演奏の意味が半減してしまう、そういう作品だからである。
作品を演劇的に考えること
技術的な意味として、メロディが転調した時、それは概ね高めの緊張した音域から、すとんと低域に落ちるフレーズの声の扱い。
作曲家が意図的にそのような転調とか音域の段差を作っているのは、そういう歌声というか語りの調子がほしいからである。
そこを良く汲み取って、声を低く或いは分厚くとかを工夫してみること。
高音域のフレーズの歌声と低音域の歌声を無意味に同質化させない、という考え方も出来るだろう。
それぞれ音高の高低には歌詞を含めた「意味」があるからである。
5点D~Eから上に跳躍するフレーズの扱い
声をそれまでの音域では前に押し出すようにしていた感覚を歌いながら、下方に押し下げる感覚に声を転換することである。
このやり方では、下あごを降ろすことや、上唇で上歯を覆うように発音する方法が、この転換に役立つだろう。
声を前に自然に歌える音域から、この5点D~E辺りに跳躍する寸前に顎を動かし、息を下に向けて吐くようなイメージである。
こうすると声が少しくぐもるが、そのことで高音の不要な鋭さが減少して、結果的に滑らかなフレーズ感が出せるだろう。
この技術が会得できると、今以上に高音発声が楽になるはずだし、喉への負担も少なくなる。
また、この方法はフレーズの高低と歌詞の意味との不整合を防ぐ意味でも、有効な方法だと思う。